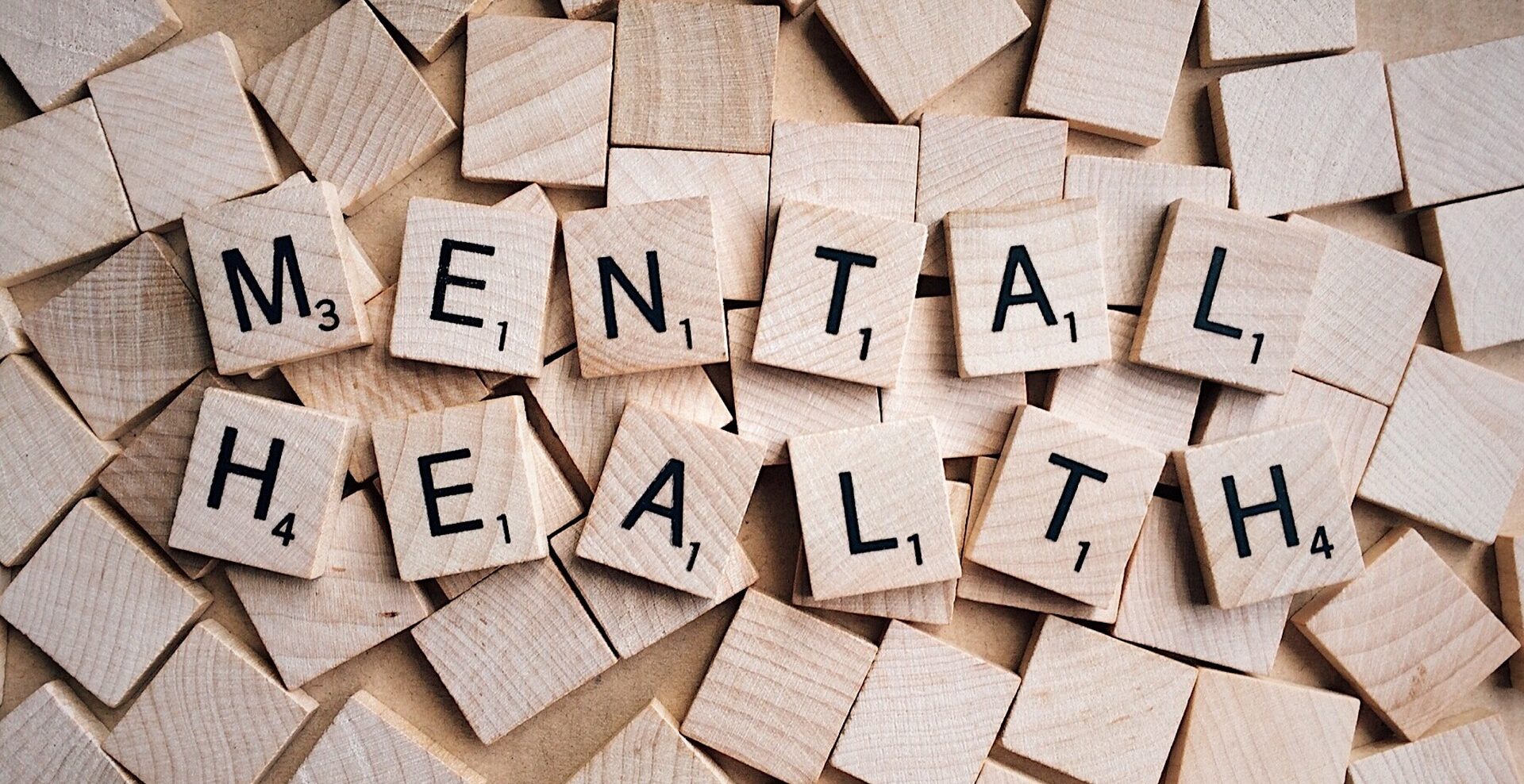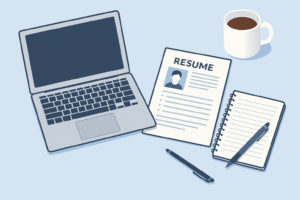【第1回】提案が通らない…上司の“正解”しか認められない職場にモヤモヤ|やりがいを感じない理由と向き合い方|キャリモヤLab

働く中でふと感じるモヤモヤや違和感。
誰かに話したいけど、相談するほどでもない…そんな気持ち、ありませんか?
このコーナーでは、日々のちょっとしたキャリアの悩みに、キャリアコンサルタントの視点でお答えしていきます。
読んでくれたあなたの「ヒント」になればうれしいです。
それでは第1回のご相談、どうぞ。
相談者からのご相談(27歳、男性)
とても仕事ができる上司がいます。
私はその上司に対して、自分なりに考えた提案を持っていくのですが、その上司にはすでに「正解」があるようで、それと一致しないとOKをもらえません。
「なんでも提案していい」と言われる社風ですが、若手の出番や育てる姿勢を感じられず、「結局、上司の求める答えを予想するゲームのようだな」と思ってしまいます。
最近は、仕事への面白みも薄れ、「こなせばいいや」と感じるように…。転職も視野に入ってきました。
キャリアコンサルタントからの返答
このご相談、実は多くの職場で聞かれる悩みでもあります。
「一見、自由に見えるけれど、実際は決まった“正解”をなぞるだけ」——これは、働く人の主体性や成長意欲を徐々に奪ってしまう環境です。
あなたが感じている「面白みのなさ」や「やらされ感」は、決してわがままでも甘えでもありません。それは、仕事において自律性を大切にしたいという、健全な成長欲求の現れです。
人が意欲的に行動するためにの3要素
心理学者デシとライアンによる自己決定理論では、人が意欲的に行動するために必要な3つの要素として、
1. 自律性(自分で選んでいる感覚)
2. 有能感(成長している実感)
3. 関係性(信頼・つながり)
があるとされます。
今回のケースでは、この「自律性」や「有能感」が満たされにくい状況にあるため、モチベーションが低下しているのはごく自然なことなんです。
人の**やる気(モチベーション)**の仕組みを研究してきたアメリカの心理学者です。
代表的な理論が、「自己決定理論(Self-Determination Theory/SDT)」。
「自律性・有能感・関係性」という3つの心理的欲求が満たされることで、人は内側からやる気を感じ、自分らしく行動できるとされます。
「仕事ができる上司」の落とし穴?
上司が優秀であるがゆえに、「正解」が最初から頭にあるというのはよくあることです。
ただ、それが行き過ぎると「答えを教えてくれればいいのに、なぜ提案させるのか?」という矛盾を生みます。これは、**“任せるフリ”**をしている状態とも言えます。
「育てる気がないように感じる」というのも鋭い感覚です。上司の仕事の進め方が「効率重視」である一方で、「育成の視点」が抜け落ちてしまっているのかもしれません。
今、立ち止まって考えてもいいタイミングかもしれません
このまま我慢して働き続けることも可能かもしれません。ただ、今感じている違和感を無視してしまうと、後になって「自分らしく働けなかった」という後悔につながることもあります。
キャリア理論であるホランドの職業選択理論では、人は自分の価値観や性格に合った環境でこそパフォーマンスを発揮できるとされています。
もし、今の環境が「合わない」と感じ始めているなら、転職を視野に入れるのも自然な流れです。ですが、すぐに動く前に、
• 自分が「どんな働き方をしたいのか」
• 「どんな上司と仕事をしたいのか」
• 「どんな場で、自分らしさを発揮できるのか」
といった自分の価値観を整理する時間を取ってみると、次のステップがより納得のいく選択になるはずです。
まとめ:
あなたの中にある「もっと良くしたい」「提案を活かしたい」という気持ちは、間違いなく“働く力”の源です。
その力を活かせる場所が、今の職場なのか、それとも別の場所なのか。
今は「考えるべきタイミング」に来ているのかもしれません。
焦らず、でも誤魔化さず、自分の声に耳を傾けてみてくださいね。