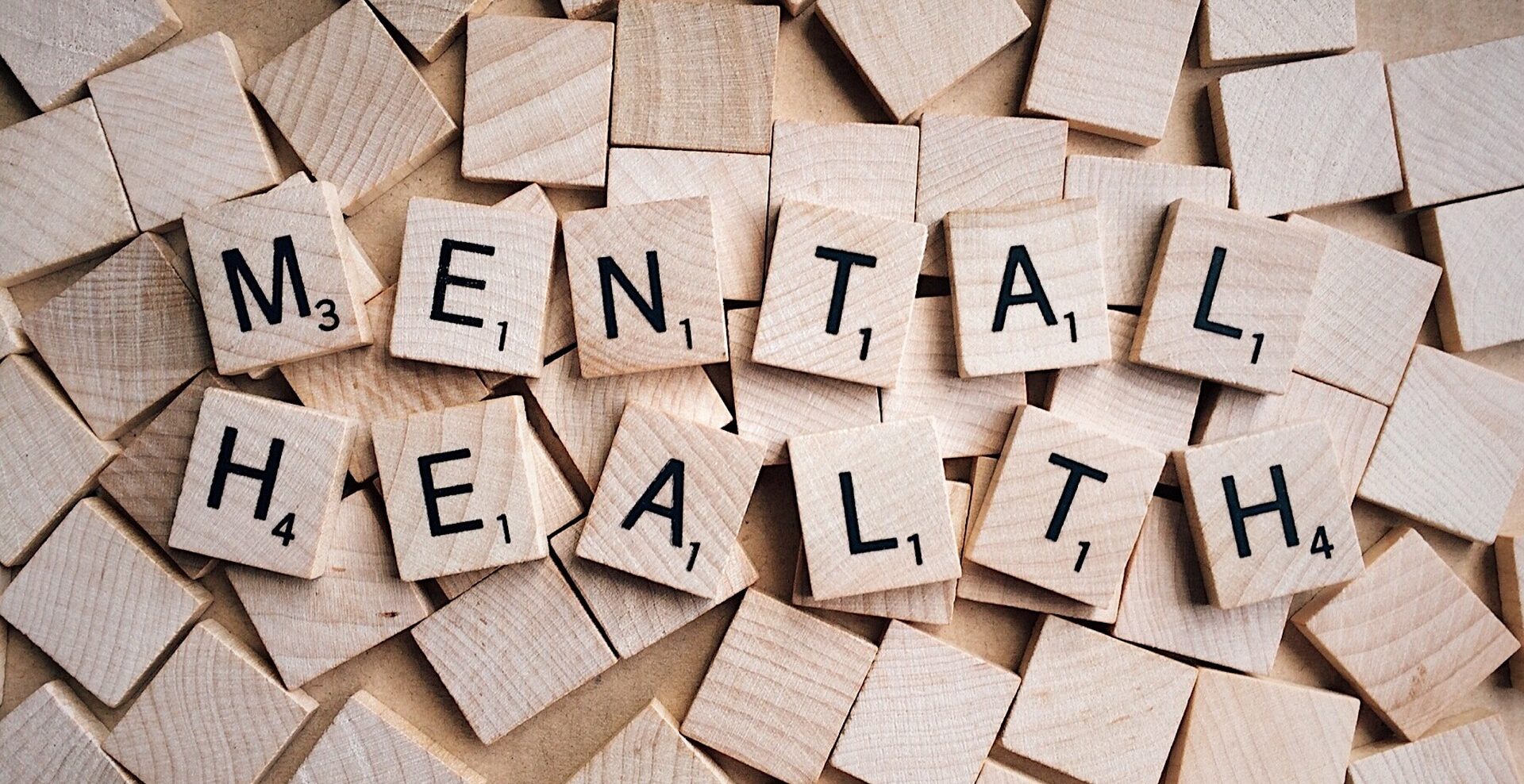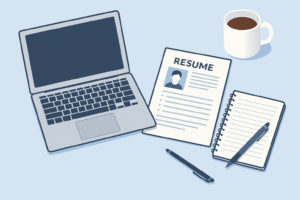【第5回】自分を出したら浮くかも?年下リーダーを立てながら“評価されない不安”と向き合う|キャリモヤLab

年下リーダーのもとで「出すか・抑えるか」に迷うあなたへ
ご相談内容(40代、女性)
「もっと自分を出していいよ」と言われた。 でも、自分が出ることで場が乱れないか、リーダーを立てることとのバランスが気になる――。
これは、職場でよくある“ポジションの壁”と“感情のゆらぎ”が交差する状況です。
今回は、年下の経験の浅いリーダーのもとで支える立場にある相談者のモヤモヤから、 「どう自分を出していけばいいのか?」というテーマを掘り下げていきます。
このモヤモヤの正体は、「調和」と「自己実現」の板挟み
相談者はとても誠実で、人間関係において「調和」を大切にしてきた方。 一方で、「自分の力をもっと発揮したい」「このまま抑え続けるのはつらい」という自己実現への欲求も抱えています。
この感情の正体は、心理学者マズローの欲求5段階説にも通じます。 社会的欲求(周囲と良好にやっていきたい)と、自己実現欲求(自分らしく貢献したい)がぶつかっている状態です。
特に職場では、次のようなジレンマが起きがちです:
- 「リーダーを立てる」vs「自分の考えを発揮する」
- 「目立ちたくない」vs「力を認めてほしい」
- 「言われたから出す」vs「自分の意思で出す」
この“出す/出さない”の狭間で、違和感や疲労感が残るのは当然のこと。
だからこそ、「自分がどう出すと納得できるか?」を見極める視点が大切です。
「出してもいい」の裏にある、リーダーシップへの期待
プロジェクトマネージャーの「もっと自分を出していいよ」という声かけ。 これは「力を発揮していいよ」というメッセージであると同時に、肩書きにとらわれないリーダーシップを期待している可能性があります。
心理学者バーナードの機能的リーダーシップ論や、現代のパーソナル・リーダーシップ論では、 リーダーとは「役職」ではなく、「影響力を発揮する存在」として定義されています。
あなたが、リーダーを立てながらもチームの全体像を見て動けているなら、 すでに「静かなリーダー」としての信頼を得ている可能性が高いのです。
どう出す?――「目立つ」のではなく「影響を与える」
ここで意識したいのは、“出す”=“目立つ”ことではないという点です。
たとえば、次のようなスタンスであればどうでしょうか?
- 「〇〇さんが判断しやすいように整理してみました」
- 「こういう進め方が合うかもしれませんが、どう思いますか?」
- 「リーダーと共有済みですが、私の方で先に準備しておきますね」
これらはすべて、リーダーを支えながらもチーム全体に前向きな影響を与える行動です。
重要なのは、「自分が出ることで誰に、どんな価値をもたらすか」。 つまり、「目立つこと」ではなく、「意味のある存在感を出すこと」なのです。
自分が“出していい”と感じられる条件とは?
最後に、自分自身に問いかけてみましょう:
- リーダーとの信頼関係が築けているとき?
- 上司が自分の役割や意図を明確にしてくれたとき?
- チームの誰かが困っていて、手を差し伸べられるとき?
このように「自分が納得して動ける条件」を明確にしておくと、 遠慮や不安に縛られず、自然と力を発揮しやすくなります。
まとめ|あなたの中には“静かなリーダーシップ”がある
あなたはすでに、「支える立場」から見える広い視野と、 「チームをよくしたい」という想いを持った、誠実なリーダーです。
完璧な肩書きがなくても、人は影響力を持つことができます。 それがまさに、オーセンティック・リーダーシップ(真摯なリーダー像)の本質でもあります。
「どう見られるか」ではなく、「どう活かせるか」へ。
それが、“出していいのか”に迷うあなたにとっての、 新しいキャリアの指針になるかもしれません。
キャリモヤLab、公式LINEができました!
公式LINEに登録すると、「なんかしんどいをやさしく言葉にするワーク」をプレゼント中!