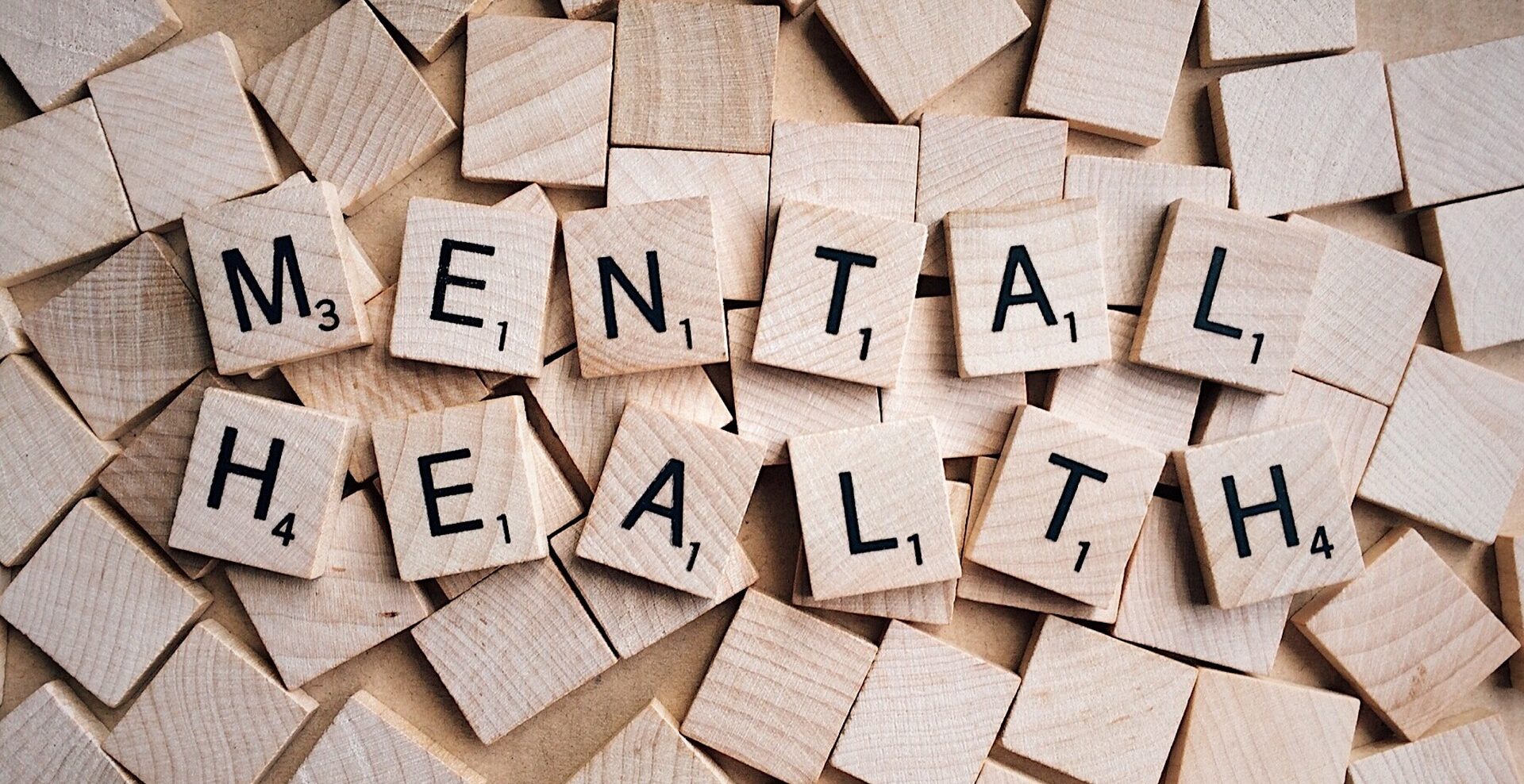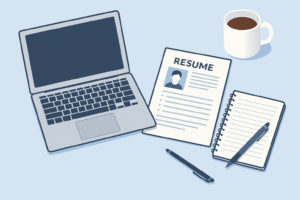【第4回】若手に仕事が流れる…評価も期待もわからない40代女性のキャリアの悩み|キャリモヤLab

評価も期待も曖昧なまま、若手に仕事が流れていく。私はこの先どうすれば?
ご相談内容(40代、女性)
これまで積み上げてきたことが、どこかで活かされているのか、最近わからなくなってきました。
日々コツコツと仕事に取り組み、トラブル対応やチームのフォローも、自分なりにしっかりやってきたつもりです。
けれどここ最近、主要な業務や新しいプロジェクトはどんどん若手に割り振られていて、自分はベテランという立場からか、支える役割に回ることが増えてきました。
そうなると、これは期待されていないということなのか、それとも単に“便利な人”として扱われているだけなのか…そんな疑問が浮かんできます。
評価されているという実感もありません。とはいえ、周囲からは「安定して働いている人」と思われているのかもしれません。
このままではキャリアが停滞しているのではという不安も出てきています。
このまま今の会社にいて、自分はどんな立場で働けばいいのか、自分の強みをどう活かしていけばいいのか——その答えが見えず、不安が大きくなってきています。
キャリアの“見えにくい成長”に気づくために
このようなモヤモヤは、**キャリアの中盤期(30〜40代以降)**に多く見られる悩みのひとつです。
かつては「昇進=キャリアの成功」という明確な図式がありましたが、現代はVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代。
働き方やキャリアの在り方も多様化し、昇進や肩書きにとらわれず、個人としてのキャリアを築いていくことが求められるようになっています。
一方で、そうした変化の中では、評価や期待が“見えにくくなる”傾向も。
役割が明確に定義されないまま日々を過ごしていると、
「自分はこの組織でどういう存在なのか?」
「何を期待されていて、どんな価値を発揮できているのか?」
といった問いがふと浮かび、キャリアの手応えや存在意義がぼやけてしまうこともあるのです。
中年期特有の「キャリアの揺らぎ」に目を向ける
心理学者ダニエル・レビンソンが提唱した「中年の危機(Mid-life Crisis)」という概念では、40歳前後のタイミングで、人はこれまでの人生やキャリアの歩みを見つめ直し、「このままでいいのか?」という内省が強くなる傾向があるとされています。
「中年の危機(Mid-life Crisis)」とは、心理学者レビンソンが提唱した概念で、おおよそ40歳前後のタイミングで、人は人生やキャリアの折り返し地点に立ち、内省が深まる傾向があるとされています。
この時期は、
・自分がこれまで選んできた道に納得できているか?
・これからどんな働き方・生き方を描きたいのか?
といった問いが自然と浮かびやすくなるのが特徴です。
これは“危機”というよりも、「これまで」と「これから」を再定義する重要な転換点。
今のキャリアや立場に対して違和感を覚えたとき、それは「変化の兆し」や「本音に気づくきっかけ」かもしれません。
それまで積み上げてきたものに誇りがある一方で、ふと立ち止まりたくなる。
このままの働き方で良いのか、これ以上どう成長していくのか、モヤモヤとした問いが湧いてくるのです。
さらに、この時期の揺らぎは、心理社会的発達理論を提唱したエリク・エリクソンの視点でも説明できます。
エリクソンは人生を8つの発達段階に分け、中年期(おおよそ40~65歳)を「世代性 vs 停滞性(Generativity vs Stagnation)」の葛藤の時期としました。
この段階では、次のようなテーマが浮かび上がります:
- 自分がこれまで築いてきたものを、次の世代や組織にどう伝えていくか?
- 社会の中で、自分の存在や役割にどんな意味があるのか?
- 成長が止まってしまったような停滞感にどう向き合うか?
つまり、「自分のこれまで」と「この先の在り方」のあいだにあるギャップをどう埋めていくかが、この時期の課題なのです。
今回のご相談も、職場環境の変化や立場の曖昧さに加えて、ちょうどこの**人生とキャリアの節目特有の“再定義のタイミング”**と重なっているのではないでしょうか。
「中年の危機」は、単なる停滞ではなく、キャリアの再構築と自己再発見の機会。
自分がこれからどんな価値を大切に働いていきたいのかを見つめ直す、豊かな成長のプロセスでもあるのです。
エリクソンは、人の一生を8つの心理社会的発達段階に分け、それぞれの時期に「乗り越えるべき心の課題」があると考えました。
たとえば40代以降の中年期では、「世代性 vs 停滞性」がテーマ。
自分の経験や価値を次世代や周囲にどう伝えていくかが、キャリアや人生の充実感に大きく影響すると言われています。
つまり、「自分のこれまで」と「これからの在り方」の間にあるギャップに目を向け、それをどう埋めていくかが、この時期特有の大きなテーマとなるのです。
今回のご相談も、職場での立場や評価の不明瞭さに加えて、まさにこの人生とキャリアの節目に起こる“再定義のタイミング”と重なっているのではないでしょうか。
「中年の危機」=終わりや停滞ではなく、キャリアを再構築し、自分らしい働き方や価値を再確認する大切なプロセス。
そのモヤモヤは、次のステップへ進むための「静かなスタート」かもしれません。
見落とされがちな“貢献”に目を向けてみる
キャリア支援の現場では、こうした状況を整理するために、ドナルド・スーパーの「キャリア成熟」という理論が使われます。
スーパーは、人のキャリアは“肩書き”や“役職”ではなく、「自己概念(=自分らしさ)」がどう育っているかによって成熟していくと考えました。
たとえば、以下のような行動は目立たなくても重要な貢献です:
- 若手がスムーズに動けるように業務を整えている
- 相談役として周囲を安心させている
- トラブル時に現場を支える存在になっている
これらは「縁の下の力持ち」的なポジションですが、組織にとっては不可欠な存在です。
スーパーは、キャリア発達を年齢や肩書きではなく、「自己概念(=自分らしさ)の発達」として捉えました。キャリアが成熟しているとは、「自分の強みや価値観を理解し、それを活かして働けている状態」。役職や成果だけでなく、内面的な納得感や成長実感も、キャリアの重要な指標とされます。
意味づけによってキャリアは変わる(キャリア構成理論)
心理学者マーク・サビカスの**キャリア構成理論(Career Construction Theory)**では、
“キャリアは経験そのものではなく、それにどう意味づけるかで形作られる”
とされています。
つまり、どんな役割であれ、
- 「私はこの役割にどんな意味を見出しているか」
- 「今の立場でどんな力を発揮しているのか」
を考えることが、キャリア実感や納得感に繋がるのです。
キャリア構成理論では、「キャリアは出来事そのものではなく、そこにどんな意味づけをするかで形づくられる」とされています。
どんな立場や経験であっても、「自分にとって意味がある」と感じられることが、キャリアの実感や成長につながるのです。
今の立場を“キャリアの土台”にする3つの視点
①「支える力」は、リーダーシップの土台
表に立つ人だけでなく、支える人もまた組織の推進力です。 チームや若手を導く姿勢は、静かなリーダーシップとして十分に価値があります。
②「実績より信頼」でキャリアを築く
昇進やプロジェクトの成果とは別に、 「この人がいると安心」「声をかければ答えてくれる」 という信頼の積み重ねが、後のキャリアの広がりに繋がります。
③「今の役割に意味を持たせる」
今のポジションを一時的な“低評価”として捉えるのではなく、
- 自分が後輩に何を伝えているか
- チームにどんな影響を与えているかに目を向けることで、意味づけの質が変わります。
40代以降のミドルキャリア期は、これまでの歩みとこれからの選択を見直すタイミングでもあります。
まとめ:今の立場でも、キャリアは育っている
評価されていないように見えるときほど、自分の中で「何に価値を感じているか」を見直すことが大切です。
キャリアとは“見えるもの”だけでなく、“意味づけの積み重ね”で育っていくもの。
40代以降は特に、これまでの歩みとこれからの選択を見直すタイミングでもあります。
あなたが今、どんなスタンスで働き、どんな影響を与えているかに目を向けることで、 たとえ立場に変化がなくても、キャリアは確実に進化しています。
“評価されるための働き方”ではなく、“自分の価値観に沿った働き方”を見つけていくことが、これからのキャリアを支える軸になるはずです。